Q1:「ひこにゃん」で有名な彦根市ですが、その「彦」という文字にはどんな意味があるでしょう?
Q2:『雲門広録(うんもんこうろく)』という文献を出典とする「日日是好日(ひびこれこうじつ)」とはどういう意味でしょう?
Q3:昭和30(1955)年には約6,000社あった醤油メーカー。令和5(2023)年は約何社?
Q4:醤油には「標準」「上級」「特級」の等級がありますが、これらは何によって分類されているでしょう?
物語
醤油の品質基準はうま味の数値で決まる
食事のときに「味に厚みがある」と感じたことはありますか?
もしかすると、味に「厚み」を感じる初めての体験を、この醤油が届けてくれるかもしれません。
さて、醤油は「甘味」「酸味」「塩味」「苦味」「うま味」の「五味」がすべて含まれているといわれる調味料です。
五味の一つであるうま味。その主な成分はアミノ酸です。醤油の醸造過程では、原料である大豆と小麦のタンパク質が、微生物によって分解され、アミノ酸、つまりうま味が作り出されています。
醤油の品質基準はうま味の数値で決まる
醤油は「甘味」「酸味」「塩味」「苦味」「うま味」の「五味」がすべて含まれているといわれる調味料です。
五味の一つであるうま味。その主な成分はアミノ酸です。醤油の醸造過程では、原料である大豆と小麦のタンパク質が、微生物によって分解され、アミノ酸、つまりうま味が作り出されています。
じつは、醤油のうま味は、数値によって表せるのをご存知でしょうか?
うま味成分のアミノ酸は窒素を含んでいるため、醤油のうま味は「全窒素分」で計ることができます。日本農林規格(JAS)によると、この全窒素分によって、醤油の等級(品質基準)が決まっており、「標準」「上級」「特級」の3段階に分かれています。さらに特級の中でも、全窒素分がより多く含まれているものは「特選」「超特選」に分類されます。濃口醤油では、窒素分が100ml中1.20g以上だと標準、1.35g以上だと上級、1.50g以上だと特級です。特級の1.1倍以上の窒素分を含む場合は特選、1.2倍以上含む場合は超特選です。
平成25(2013)年3月時点で、JAS規格認定製造業者数は576者、格付数量は474,101klです。日本の醤油製造業者数は約1,500者、平成24年の醤油出荷数量は807,060klなので、JAS認定を受けている業者の割合は約38%、JAS規格を得ている醤油は約59%となります。
また、特選、超特選は表記が任意であるため、基準を満たしていても「特選」「超特選」の表示をしていない醤油もあります。
ですので、正確な割合はわかりませんが、最も等級が高い超特選は、JAS認定を受け得ている6割の醤油のうち、さらに追加で基準を満たしたものであるため、割合としては少なくとも半分以下になると考えるのが自然といえるのではないでしょうか?
味の違いに興味がある方は、ぜひ一度、超特選の醤油を味わってみてください。
味に「厚さ」を感じる醤油
さて、ここでご紹介する「日日是好日(ひびこれこうじつ) 濃口醤油」は、成分分析の結果、ほかの醤油より全窒素分がかなり高いことが分かっており、超特選に値します。しかし、なぜこの醤油のうま味成分がこれほど高いのかは、はっきりとは分かっていません。ここが醤油をはじめ発酵食品の奥の深さです。おそらく、蔵に住み着いている菌の影響だと考えられています。
また、この醤油は、五味がバランスよく引き立つよう意識して作られています。
醤油作りにおいて重要な工程を表す言葉として「一麹(いちこうじ)、二櫂(にかい)、三火入れ(さんひいれ)」という言葉があります。まずは良い麹を作ることに徹し、次に適切なタイミングで櫂入れ(撹拌作業)を行い、最後に火入れによって香りを立たせて味のバランスを整えます。
この品物の場合、醤油になるまで約2年間に渡って櫂入れが行われます。また、小さな違いや変化に気づくため、撹拌には機械を使わずに、全量手作業で行っています。
こういった手作業での櫂入れによって、醤油の味に影響を与え、醤油が備え持つ五味を引き出せるそうです。
実際にこの醤油を味わった人からは「味が濃い」「厚みがある」といった感想が多くあがります。もちろん、味の感じ方は人それぞれですが、この品物の味の濃さ、うま味の強さは、少なくとも数値にも表れているようです。
あなたなら、この醤油の味をどのように表現するでしょうか?
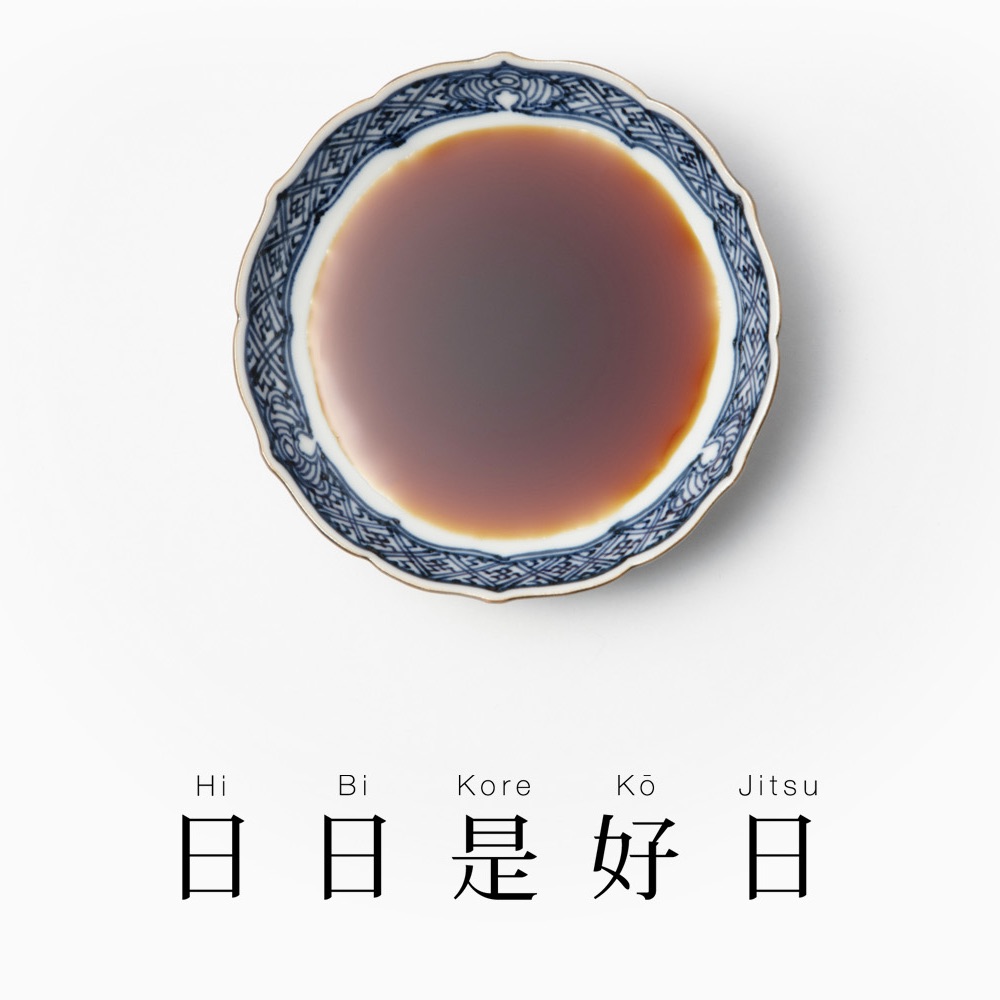
禅の教えから生まれた「日日是好日(ひびこれこうじつ)」
この非常に高いうま味数値を持つ稀有な醤油の作り手は、水谷醤油醸造場(滋賀県)。この醸造場が提供する、醤油をはじめとする品物は、「日日是好日」がコンセプトに掲げられています。
「日日是好日」という言葉は、宣和2(1120)年前後に出版された『雲門広録』が出典です。『雲門広録』は、中国の唐の時代(864~949年)に活躍した禅僧、雲門文偃(うんもんぶんえん)の言行録です。
ある日、雲門文偃が弟子に向かって、「これまでのことは一旦聞かないので、これからのことをただ一言で言ってみなさい」と言いました。しかし、弟子は答えられなかったので、雲門文偃本人が代わりに答えた言葉が「日日是好日」です。
「日日是好日」は、おおむね「毎日が素晴らしい」という意味です。しかし、何か悪いことが起きたり、天気が悪かったりして、素晴らしい毎日が続くことはそうないでしょう。そんな日でも、平穏に暮らせるような心を持つのが大事だ、といったことを伝えるのが「日日是好日」という言葉です。
床の間の起源とは
「日日是好日 濃口醤油」のパッケージデザインは、前述した「日日是好日」という言葉のイメージや、作り手の品物への思いなどを考慮して作られています。掛け軸のある床の間、日本の茶室がイメージされており、紙種は雲龍紙という和紙を使用しています。
ちなみに、床の間とは和室に設けられる、掛け軸や花瓶、置物などを置く空間で、座敷の床が一段高くなっているのが特徴です。
床の間の起源や名前の由来には諸説あるようです。元々、床(とこ)の間の「床」には「座る、寝るところ」といった意味があり、それが転じて、身分の高い人が座る、一段高くなった床張りの場所を「床」と呼ぶようになりました。それが次第に「床の間」と呼ばれるようになったというのが一つの説です。また、古代の民家では仏具や位牌を床の間に飾っていたことから、床の間はもともと仏壇のようなものだったのではないかともいわれています。

滋賀県彦根市周辺の湿潤な環境と産品
水谷醤油醸造場は、滋賀県彦根市日夏町で醤油作りを行っています。鈴鹿山脈から琵琶湖に注ぐ、犬上川と宇曽川の二つに挟まれた土地です。

ご存知の通り、滋賀県には総面積の約6分の1を占める、日本最大の湖「琵琶湖」があります。そのため、水資源が豊富です。その水資源を活かして、滋賀県では米、小麦、大豆、そして醤油などが作られています。
醤油作りにおいて欠かせない麹菌などの菌類は、基本的に気温25〜28度、湿度70%以上で一気に増殖する場合が多いとされています。麹菌の力を借りる醤油作りにおいて、環境が湿潤であることは、大切な要素の一つです。
「彦根」の由来は日本神話から
ところで、滋賀県彦根市の「彦根」の由来は、日本神話にまで遡ります。天照大神(あまてらすおおみかみ)の御子に天津彦根命(あまつひこねのみこと)、活津彦根命(いきつひこねのみこと)の二神がおり、このうち活津彦根命が活津彦根明神として山に祭られました。その山が彦根山であり、彦根山がある一帯の地域も彦根と呼ばれるようになったといわれています。
ちなみに、彦根の「彦」は、じつは男性に使う美称で、「才徳のすぐれた人」などの意味を持ちます。現代でいうと「イケメン」くらいの意味を持ちます。元は「日子」だとする説もあり、偉大な太陽の神の子という意味だそうです。対義語は「姫」で、こちらも「日女」で太陽神の娘という意味だったそうです。
水谷醤油醸造場の木桶仕込み復活に向けた挑戦
さて、「日日是好日 濃口醤油」は、国内の生産量が極めて少ない、木桶仕込みで作った天然醸造の醤油です。夏を2回、冬を1回経る、二夏一冬(ふたなつひとふゆ)醸造という製法で、2年以上の歳月をかけて作られています。
天然醸造は、「日本農林規格等に関する法律」によって定義されており、「本醸造の製法によって作られている」「酵素の添加や醸造の促進を行っていない」「食品添加物を使用していない」の三つを満たしている醤油だけが、天然醸造と名乗ることができます。
では、この貴重な醤油は、どのように誕生したのでしょうか。
水谷醤油醸造場の創業は嘉永6(1853)年。黒船来航と同じ年です。その時代では当然、醤油の仕込みには木桶が使われていました。しかし、時代が変化するにつれて、木桶よりもステンレスや強化プラスチックの桶の方がコストが低いなどの理由から、木桶仕込みの醤油はどんどん少なくなっていきました。2021年時点では、木桶を使用している醤油メーカーは、全体の1%ほどだとされています。このままでは、木桶で醤油を作るという日本の技術が途絶えてしまうこともありえます。
水谷醤油醸造場も、1970年ごろには木桶仕込みをやめたそうです。しかし、2020年になり、本物の味を追求しながら醤油作りをする中で、木桶を用いた伝統的な製法が本質的に必要だと感じ、約50年の間行っていなかった木桶仕込みを復活させました。
じつは、水谷醤油醸造場には、約50年前まで使用していた木桶が数本だけ残っていました。水谷さんは、酵母などの菌がまだ残っているかもしれないと思い、その木桶で醤油を仕込んでみたところ、やはり菌がいてくれたのでしょう、味や香り、風味などが想像以上の出来になりました。こうして出来た醤油に、コンセプトでもある「日日是好日」という名前を付けました。
また、50年前の木桶で仕込んだ醤油の「もろみ」を絞りきらずにあえて残し、新たに導入した木桶にも種もろみとして加えたことで、今でも同じ味や香りが引き継がれています。

一度途絶えた木桶仕込みを復活させたという前例は極めて少なかったので、すべて一から手探りで進めていったそうです。
新たに道具を導入することでかかる費用や、道具に合わせた製法の調整など、さまざまな壁があるなかで、木桶で再び醤油を作るというのはとても大変です。お金と手間をかけてこれまでの環境を変えていくというのは、一般には、なかなかできることではないのではと感じます。
そのときのことを水谷醤油醸造場6代目の水谷優太さんに聞いてみたところ、「今思い返せば大変だったかもしれませんが、その状況もワクワクしてすごく楽しかったですね」と語っていました。本物へ少しでも近づこうとする姿勢が、巡り巡って産業を守ることにつながっているのではないかと思わされます。
最後に
ところで、醤油の作り手は、年々減少傾向にあります。企業(工場)数は、昭和30(1955)年には約6,000社あったのが、令和5(2023)年には1,035社になっています。これは、日本の人口が減っていることももちろん、食の多様化、洋風化からくる和食(特に、大量に醤油を使う煮物)離れが原因の一つではないかとされています。需要が減っているぶん、供給も減っている状態です。
さらに、前述した通り、木桶で醤油を仕込むという、昔ながらの製法をとっている作り手は非常に少なくなっています。
そんな状況下での6代目水谷さんの挑戦や、その挑戦を「楽しかった」と言える姿勢は、同じように何かに挑もうとしている人にとっては、勇気を与えるものなのではないでしょうか?
水谷醤油醸造場からのメッセージ
年を重ねるごとに、全国にファンのお客様が増えていることを感じています。今後は、シンプルに「美味しい醤油」を探求して作り続けたいです。発見物語が、このお醤油を知ってもらう一つのきっかけになればうれしい限りです。
日々のお料理の中で、このお醤油を使って美味しい料理を作ってもらうことで「なんだかんだ今日も良い一日だったな」と感じていただけたらと思っています。
お召し上がり方
一般的な醤油と同じようにお使いください。
おすすめのお召し上がり方:まずは醤油本来の香りや味を楽しむため、匂いを嗅いだり、小皿に入れて少し舐めてみたり、冷奴や卵かけご飯(やや多めがおすすめ!)などのシンプルな料理に使うことをおすすめします。これを機に、複数の種類の醤油を使い分ける生活を始めてもらえればうれしく思います。
基本情報
価格:¥540(税込)
容量:100ml
名前:こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料:大豆(国産)、小麦(国産)、食塩
賞味期限:通常、製造から1年以内
保存方法:直射日光を避け、常温で保存
栄養成分(100g当たり):
熱量 89.2kcal
たんぱく質 10.3g
脂質 0.0g
炭水化物 12.0g
食塩相当量 18.1g
A1:「彦」は、男性に使う美称で、「才徳のすぐれた人」などの意味を持ちます。元は「日子」だとする説もあり、偉大な太陽の神の子という意味だそうです。
A2:おおむね「毎日が素晴らしい」という意味ですが、どんな日でも、平穏に暮らせるような心を持つことが大事だ、といったことを伝える言葉でもあります。
A3:令和5(2023)年では1,035社です。
A4:「全窒素分」という、醤油のうま味を表した値で分類されています。
「日日是好日 濃口醤油」についてのお便りやご質問
「日日是好日 濃口醤油」のご感想やご質問、おすすめのお召し上がり方などをお送りください。
※発見物語のWEBサイトやメールマガジン、弊社発行物などでご紹介させていただくことがあります。ペンネームをご希望の方はペンネームをお書きください。
※その他、弊社へのご質問や発送状況のお問い合わせなどは「お問い合わせ」からお願いいたします。



